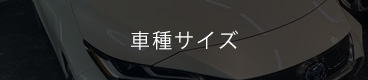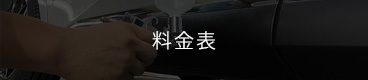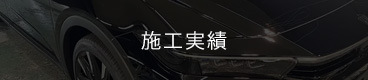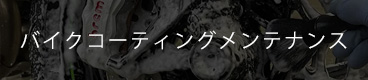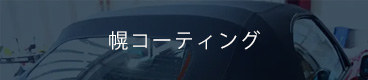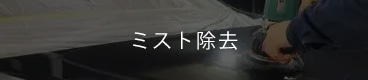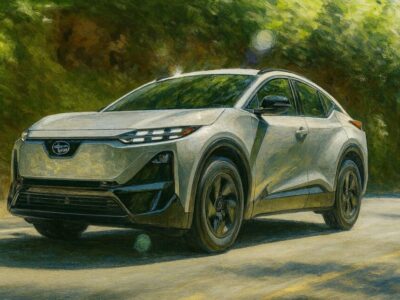GT-Rは電動化の時代へ──それでも魂は失われない

2025年4月、ニューヨークオートショーの舞台で、日産のアメリカ部門副社長であり最高企画責任者でもあるパンジ・パンディクティラ氏が次期GT-R(通称R36)について明言しました。ついにGT-Rがハイブリッドとして生まれ変わることが正式に決定されたのです。これは単なるモデルチェンジではなく、GT-Rという伝説的スポーツカーが「電動化」という現代の技術革新とどう向き合うのかを示す、重要な分岐点に立っていることを意味しています。
電動化の流れは避けられません。しかし、それでもGT-Rは”らしさ”を捨てませんでした。実は一時期、完全EV(電気自動車)化の案も検討され、開発プロトタイプも製作されていたそうですが、パンディクティラ氏によれば「ニュルブルクリンクを1周したら充電が必要になる」レベルだったとのこと。充電時間と走行持続力、熱管理の課題がパフォーマンス重視のGT-Rとは相容れなかったのです。
GT-Rといえば、あの鋭い加速力、路面を食いつくように走る四輪駆動、そしてサーキットでポルシェ911を凌駕する走行性能──これらすべてが求められるモデルです。その理想の実現には、現状のバッテリー技術(たとえ全固体電池であっても)ではまだ不十分。結果、ガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッド、もしくはプラグインハイブリッドという選択肢が現実解として浮かび上がったのです。
これは単なる技術的な選択ではありません。GT-Rは「日常の足としても使えるスーパーカー」であり続けることを重要視しています。買い物や通勤、子どもの送迎にも使え、それでいて週末にはサーキットを駆ける。そんなクルマこそがGT-Rであるべきだという思想が、今回のハイブリッド化の裏にはあるのです。

私たちのようなクルマの外装保護に関わるコーティング専門店から見ても、GT-Rのような名車がこれからも走り続けてくれるのは非常に嬉しいことです。電動化によって、車体下部やバッテリー周辺の防錆・熱保護の重要性もますます高まってきています。たとえばSOUPのセラミックコーティングでは、従来の塗装保護に加え、熱によるダメージ軽減や融雪剤などによる塩害対策としても効果を発揮します。
R36 GT-Rがどのような形で誕生するにせよ、その真価は「走らせてこそ」わかるクルマであることに変わりはありません。私たちのような現場の専門店にとって、そうした本物の走りを守るためのコーティングは、まさに“共に進化する存在”でありたいと思っています。
GT-Rはハイブリッドか、PHEVか──進化するパワートレインの選択肢

次期GT-Rが電動化されることは明らかになったものの、その仕組みがハイブリッドになるのか、それともPHEV(プラグインハイブリッド)になるのかは、まだ最終決定に至っていないようです。パンディクティラ副社長は「理想はPHEV」と語りながらも、「現時点の技術ではトラックユースに向かない」と現実を直視しています。PHEVは電池容量が大きいため重くなりやすく、例えばニュルブルクリンクを2〜3周走るとバッテリーが空になってしまうという課題があるのです。
その点、通常のハイブリッドであれば、バッテリーの容量こそ小さいものの、ガソリンエンジンとの組み合わせによって連続した走行が可能で、現実的なサーキットパフォーマンスに対応できます。GT-Rのような“走り”が命のモデルでは、この点が非常に重要です。日産は次世代バッテリー技術、特に「全固体電池」の実用化に向けて取り組んでおり、その進展がGT-Rの仕様を左右することになります。
理想像としてパンディクティラ氏が挙げたのは「街乗りでは70マイル(約112km)をEVとして走れるGT-R」。日常では静かで環境に優しく、週末にはサーキットで牙を剥く──そんな二面性をもったスーパーカーです。そのためには、軽量かつ高出力なバッテリーと、優れた熱管理技術が必要不可欠です。
そしてGT-Rの象徴ともいえるのが、あのツインターボV6エンジン。R36にもこの遺伝子は継承される予定で、「火を噴くようなV6ツインターボを搭載する」とパンディクティラ氏も明言しています。最新のアーミーダ(北米向けSUV)に搭載された新開発V6ターボユニットは、GT-Rの血統を感じさせる設計となっており、排ガス規制にも2032年まで対応できるクリーンさを実現しています。

私たちSOUPのようなコーティング専門店が注目しているのは、こうした高性能エンジンを搭載する車両の熱や化学的ストレスに対応したコーティング技術です。特にボンネット周辺やフェンダー内部など、熱の影響を受けやすい箇所には、耐熱性に優れたセラミックコーティングの施工が効果的です。さらにPHEVであれば充電ポート周辺のケアも欠かせません。
またGT-Rは「全天候型スーパーカー」としても知られており、雨天や積雪時にも日常使いが可能です。そうした環境でも車体を保護するためには、セラミックコーティングによる撥水・防汚効果が大きな力を発揮します。特に冬場の凍結防止剤(塩カル)から車体を守るには、下回りの防錆施工との併用がおすすめです。
技術と哲学の両面で進化を遂げようとしている次世代GT-R。その性能を最大限に引き出すためには、購入後のメンテナンスや保護も同じくらい重要だと、私たちは考えています。
“ゴジラ”の再来はいつ?──R36 GT-Rとその進化を支えるメンテナンスの未来

パンディクティラ副社長が示したR36 GT-Rの登場予定時期は「今後3〜5年以内」。このタイミングは、日産が現在開発中の全固体電池の量産開始計画(2028年予定)と見事に一致しています。つまり、新型GT-Rは従来の価値観と未来技術が融合する、“橋渡し的存在”として登場することになるのでしょう。
現時点で明言されているのは、「600馬力超のツインターボV6を搭載するハイブリッドスポーツカー」という姿。高性能を維持しながらも環境規制に対応し、街乗りも快適にこなせる実用性を兼ね備えたGT-R。それは一見すると矛盾しているようで、実は現代のユーザーが最も求めている“理想のスーパーカー”像なのかもしれません。
「ニュルブルクリンクを何周も本気で走れること」「雪道でも不安なく使えること」「所有していることに誇りを持てる存在感」。GT-Rという車が持つべき哲学は、どれも時代が変わっても失ってはならないものばかりです。そして、その哲学がそのまま「R36」に引き継がれるのであれば、私たちもまた全力でその価値を守りたいと考えています。

SOUPのセラミックコーティングは、見た目の美しさを保つだけではなく、GT-Rのような高出力車のボディを長期間にわたって守る“鎧”のような存在です。例えば、強烈な紫外線や酸性雨、鉄粉、虫の死骸、ブレーキダストなど──GT-Rがサーキットや高速道路で受けるダメージは計り知れません。それらを長期間にわたってガードするには、ただのワックスや簡易コーティングでは役不足なのです。
さらに、ハイブリッドやPHEVといった電動化車両には、新たな「守るべきポイント」も生まれます。充電ポートまわり、バッテリーユニット付近、そして静音性が高まった分だけ目立ちやすくなる微細なスクラッチなど──そうした細部まで配慮できるのが、SOUPのセラミックコーティングの強みです。
新型GT-Rが発売される日が来たら、きっと多くのオーナーが「この車を長く大切に乗りたい」と願うはずです。その思いに応えるためにも、私たちはGT-R専用のコーティングプランを今から構想しています。車両価格もおそらくプレミアムなものになるでしょうが、それだけの価値があるクルマだからこそ、コーティングという形で“資産価値”を守ることも、これからのスタンダードになると確信しています。
GT-Rの未来は、加速性能だけでなく「美しく、守られながら、長く走ること」が問われる時代へと突入しています。SOUPとして、その進化のパートナーであり続けたいと強く願っています。