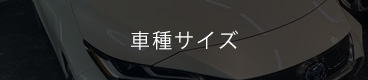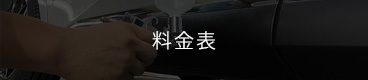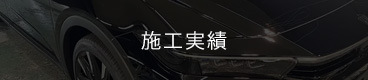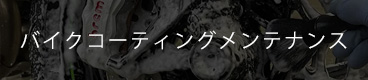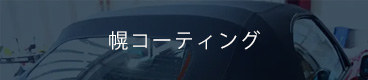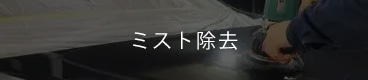EVネーミングの迷走とトヨタの「bZ」からの撤退

近年、自動車メーカー各社が電気自動車(EV)への本格的なシフトを図る中で、私たち整備業界の立場から見ても感じるのが、そのネーミングに対する迷走ぶりです。確かに電動化への挑戦は大きな転換期であり、技術的にもブランド的にも新たな価値を打ち出そうとする動きは理解できます。しかし、その一環としての車名の刷新は、必ずしもユーザーやファンに歓迎されたとは言えません。
たとえばトヨタが打ち出した「bZ」シリーズ。これは「beyond Zero=ゼロを超えて」という理念に基づいたネーミングですが、第一弾として登場した「bZ4X」という名前は、その意味や分類が一般ユーザーには非常に伝わりづらいものでした。2026年モデルではすでに「4X」の部分を削除し、さらに今後は「bZ」そのものも段階的にフェードアウトする方針が発表されています。
我々のようなコーティング専門店でも、車名が安定しないと、施工記録の管理やブランド訴求に支障が出ることがあります。「bZ4X」と依頼されても、実際には改名後のモデルである可能性があり、その違いが外観からでは判断できないケースもあるのです。そうなると、施工対象車両の確認やパーツの取り扱い、さらにはコーティング剤の選定にまで影響を及ぼします。

たとえばSOUPでは、車種に合わせた最適なセラミックコーティングを提案しています。ボディの素材や塗装の特性、デザインのラインなどを丁寧に把握したうえで施工を行いますが、その際に車名が不明確だったり、従来の名前と異なる場合、施工計画に狂いが生じる可能性があるのです。
もちろん、車名変更はブランド再構築の一環として重要な戦略であることは承知しています。ただし、ユーザー視点、メンテナンス視点、さらには私たち現場の施工者視点から見ても、親しみやすく、記憶しやすい名前が望ましいと感じます。プリウスという名前が長年にわたって愛されてきたことを思えば、わざわざ「bZ」といった新しい枠組みに挑戦するより、既存のネームバリューを活かした方が、結果的には車の魅力を引き出すことにつながるのではないでしょうか。
そして、このようなモデル名の変更が与える影響は、単なる名前の話にとどまりません。実際に現場でセラミックコーティングを行う者としては、車両の仕様や構造に関する情報収集にも時間がかかるようになり、作業効率の低下にもつながります。これは、今後さらに電動化が進む中で、メーカーと施工業者、ユーザーとの間の情報共有が一層重要になってくることを意味しています。
今後も新しいEVが次々に登場するなかで、私たちSOUPではどのような名前が付けられた車種であっても、その車の本質を見極めたうえで最適なコーティングを提供してまいります。そして、ただ美しく仕上げるだけではなく、日々のメンテナンスや再施工においても、車名や仕様に惑わされることなく、安心して任せていただけるよう努めてまいります。
電動化時代の到来は歓迎すべきことです。しかし、それと同時に、ユーザーに寄り添い、わかりやすさと信頼性を両立させたクルマづくりが今こそ求められているのではないでしょうか。
VWの「ID」シリーズの混乱と、現場で感じる違和感

次に取り上げたいのが、フォルクスワーゲン(Volkswagen)の「ID」シリーズです。トヨタの「bZ」と同様に、VWも電動化に向けて新しい命名体系を立ち上げました。「ID.4」「ID.3」「ID. Buzz」など、すべてのEVに「ID」の冠を付けてブランドを統一しようとしたのです。
ですが、こちらも結果として混乱を招いてしまいました。特に、アルファベットと数字の組み合わせに加え、ピリオドやスペースの使い方が一貫していなかったことは、現場にいる私たちのような技術者や顧客にも大きな影響を与えました。「ID.4」と表記されることもあれば「ID 4」や「ID4」とも書かれるなど、資料によって表記が異なるため、部品発注や施工記録の整理の際に混乱を招いたのです。
さらに、この「ID」シリーズには、ユーザー目線でのブランド親しみやすさが欠けているという問題もあります。かつての「Golf(ゴルフ)」や「Polo(ポロ)」のような歴史と親しみを持つ車名とは違い、機械的で抽象的な印象を受ける「ID」の名称は、愛着を持ちづらいという声も耳にします。
セラミックコーティングを行う私たちとしても、こうしたブランドとの距離感の変化は無視できません。車への愛着が深いオーナー様ほど、コーティングの必要性を理解してくださいます。しかし、「ID.〇〇」といった型番のような車名では、オーナーとの感情的な結びつきが生まれにくく、それが施工意欲にも影響しているように感じることがあるのです。
その点、フォルクスワーゲンは2025年以降、「ID」命名から脱却し、従来の車名に戻す方針を明らかにしました。つまり「Golf」や「Jetta」のような名を冠したEVが今後登場していくことになります。これは私たちのような施工業者にとっても、顧客対応の明確化、記録管理の簡素化という点で非常にありがたい流れです。

たとえば、ゴルフという車名であれば、世代を超えて長く乗り継がれるモデルですので、SOUPでも過去の施工履歴や塗装傾向をすぐに参照できます。それにより、ボディ形状に合わせた下地処理、ホイールやドア内側の施工まで、より精密なプランニングが可能になります。
命名は単なるデザインや言葉遊びではなく、実務にも直結する「情報のインターフェース」であると、私たちは感じています。車名ひとつで施工の質が変わることもあるのです。VWが「ID」命名を見直したことは、私たち現場の施工者にとっても歓迎すべき英断であり、より親しみやすく記憶に残る車との出会いをサポートする第一歩だと考えています。
EV時代の本格化が進む中でも、車名という「顔」が持つ力を軽視せず、オーナーの愛着や、私たちのような職人の精度にも影響する重要な要素であることを改めて感じる機会となりました。
Mercedes・Audi・GMの命名迷走とコーティング現場でのリアルな影響

最後に触れておきたいのが、メルセデス・ベンツ、アウディ、そしてGM(ゼネラルモーターズ)による電気自動車の命名戦略です。どのメーカーも独自の方針を掲げながらも、それをうまく活かしきれず、最終的には撤回あるいは修正する形となっています。
まずメルセデス・ベンツは、かつて「EQ」シリーズというサブブランドをEVの主軸に据えようとしました。しかし、いざ市販される段階では、「EQG」ではなく「G580 with EQ Technology」といった冗長で意味不明な正式名称が採用され、混乱を招くことになりました。
我々のように現場で車両を扱う立場からすると、こうした名称の変化や統一性のなさは、モデル判別を難しくする原因になります。お客様から「EQGでお願いしたい」と言われても、正式名称が違えば情報検索やパーツ確認に余計な時間がかかるのです。しかも「EQ」バッジ自体も車両に付いていないケースもあり、視覚的な確認すら困難になります。
セラミックコーティングの施工は、車両の形状や塗装素材だけでなく、メーカーの技術的な特徴にも対応したアプローチが必要です。SOUPでは常に最新の車両情報を収集していますが、車名が曖昧であればあるほど、現場の判断にブレが生じやすくなります。

次にアウディ。2023年に発表された「奇数=ガソリン車」「偶数=電気自動車」というルールは、ユーザーにも現場にも混乱をもたらしました。たとえば、長年親しまれてきた「A4」が、次世代ではEVでないため「A5」へと名前が移されるというのは、ブランドの一貫性を損なうだけでなく、整備・施工現場でも混乱を招きます。
車名が変更されると、塗装データや補修記録なども名称に紐づけられた情報が引き継がれにくくなります。これは単に見た目をキレイにするだけの話ではなく、安全性や耐久性に関わる重要な判断材料が抜け落ちるリスクを意味します。
アウディも最終的には「e-tron」というサフィックスを活用した命名に戻すことを決定しました。これはある意味では原点回帰であり、やはりユーザーにも施工者にも分かりやすく、検索や記録にも適した名称の方が長く愛されるのだと実感しています。
そしてGM(ゼネラルモーターズ)。彼らは車両名ではなく「Ultium(アルティウム)」というバッテリーシステム名を全面に出していました。クールな響きではありましたが、最終的にはこれも中止。ユーザーにとっても施工現場にとっても、あまり意味のないワードになってしまいました。
EV時代のバッテリーテクノロジーは進化を続けており、SOUPでも電動車両特有の放熱構造や重量バランスを考慮した施工を実施しています。特に高圧バッテリーの搭載位置や、ボディ剛性への影響など、外装の状態を見極める際に知識と経験が必要です。にもかかわらず、「Ultium」という名称がどの車両に搭載されているかが不明確であれば、施工側としても対処が後手に回ってしまう危険性があります。
命名の統一性とわかりやすさは、ブランドの信頼性だけでなく、現場の施工精度やスピードにも直結します。メーカーが再び既存のブランド名やシンプルな構成に戻る動きは、私たちにとっても朗報です。
今後もSOUPでは、どんな名称であっても車両の本質を見抜き、セラミックコーティングでその魅力を最大限に引き出すサポートを続けてまいります。名前が変わっても、車への愛情と職人の技術が変わることはありません。見た目だけでなく、価値ある保護を届けること。それが私たちの使命です。