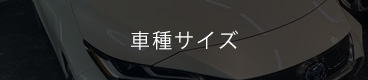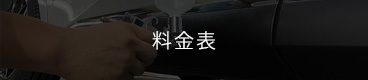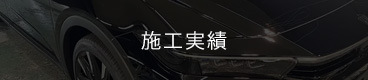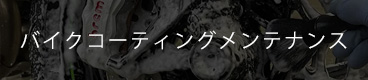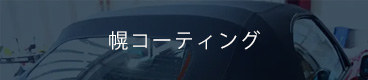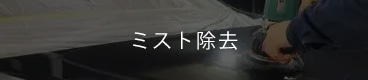スーパーチャージャー搭載!Kawasaki Teryx H2がもたらすUTVの新時代

2025年、Kawasakiが放つ最新のサイド・バイ・サイド「Teryx H2」は、ただのUTVではありません。Ninja H2スーパーバイク譲りの998ccスーパーチャージャー付き4気筒エンジンを搭載し、最大出力は驚異の250馬力。この数字は、Polaris RZR Pro Rの2.0L自然吸気エンジン(225馬力)やCan-Am Maverick Rのターボエンジン(240馬力)をも凌駕し、いま最もパワフルな量産UTVといえるでしょう。
このマシンが持つエンジンは、Kawasaki独自開発の遠心式スーパーチャージャーによって圧縮空気を最大2.4気圧(約35psi)まで送り込む設計で、9,500rpmでの高回転まで息切れ知らず。そのスーパーチャージャーは、なんとエンジン回転数の13.6倍、約13万回転に達するというから驚きです。さらに、ECU制御によるブローオフバルブが過剰なブースト圧を安全に逃がしてくれるため、安定した走行性能も確保されています。
この高出力を受け止めるために、Teryx H2は通常の単一スロットルボディではなく、40mmのスロットルボディを4基独立配置。燃料噴射も2段階構成で、低回転域ではダウンストリーム型の12ホールインジェクター、高回転域(5,000rpm以上)ではアップストリーム型10ホールインジェクターを作動させることで、空燃比を冷却しながら効率よく燃焼室に届けます。この緻密な設計は、単なるスペック勝負ではなく「扱いやすさ」と「燃焼効率」を徹底的に突き詰めた結果なのです。
SOUPの現場でも、こうしたハイパワー車両のコーティングには、通常のメンテナンスでは対応しきれない課題が出てきます。例えば、ブースト圧の上昇に伴ってエンジン熱や排気ガスの温度も跳ね上がり、樹脂パーツや塗装表面に与える影響は想像以上です。そういった熱や酸化のリスクに対して、セラミックコーティングの熱耐性と耐薬品性が、頼れる防護壁となります。さらに、SOUPで施工しているガスプライマーは塗装面との密着性を飛躍的に高めるため、スーパーチャージャー車両のような過酷な使用環境でも長期にわたって艶と保護性能を維持できます。
Teryx H2のようにエンジン特性が鋭く、パワーがピーキーな車両であっても、ミッションはCVT(無段変速機)を採用している点も興味深いです。一般的にスポーツ走行向けにはDCTやトルコンATが好まれますが、KawasakiはCVTに対して太さ17.6mmのベルトを採用し、耐久性と信頼性を確保。また、専用のスノーケルエアインテークを設けることで、冷却性能も強化されています。これはまさに、オフロードの現場を知り尽くしたエンジニアの設計思想の結晶です。
そして、こういった高度なメカニズムを備えるからこそ、車両を外的要因から守る「施工の質」がますます重要になります。見た目だけではなく、走行中に飛び石や砂塵が当たっても傷みにくい表面保護層。特にTeryx H2のようなホワイトやメタリック系のボディカラーには、セラミックコーティングとガスプライマーの併用が不可欠といえるでしょう。
電子制御と走破性が融合した次世代UTV──Teryx H2の驚異の走行性能

Kawasaki Teryx H2の魅力は、エンジンパワーだけにとどまりません。走行状況に応じて出力を制御できる「フル/ミッド/ロー」の3段階のパワーモードを搭載し、トレイルや高速ダートなどあらゆる地形に応じたセッティングが可能です。特に、ローは全出力の60%、ミッドは80%に制御されており、急峻な山道や狭い林道などでのコントロール性を大幅に向上させています。
このような切り替えが可能な点は、スポーツカーのマルチマップECUやスロットルマップ切替機能に近い感覚で、UTVの世界でも一気に洗練された印象を与えています。さらに、前後駆動切替(2WD⇔4WD)も走行中にオンザフライで切り替え可能。フロントデフロックも装備されているため、滑りやすい泥濘地や岩場でのトラクション確保も万全です。
そして、もうひとつの大きな魅力が足回りです。Teryx H2は、フロント23.2インチ、リア24.0インチのホイールトラベルを持ち、Fox製3.0インチ内部バイパスショックを標準装備。上位グレードの「デラックスモデル」には、電子制御のライブバルブ機構付きサスペンションが採用されており、走行状況に応じて減衰力を自動で調整。これは、スポーツSUVやオフロードトラックにも採用されている技術で、UTVとしては非常に先進的な装備です。
また、タイヤには33インチのMaxxis製を採用し、グリップ力と衝撃吸収性能を両立。全長159.4インチ、全幅74.0インチ、ホイールベースは126インチという設計は、PolarisやCan-Amと比べて若干コンパクト。これは狭い林道や日本の山間部での取り回しにおいて、確かなアドバンテージとなるでしょう。
こうした高度なサスペンションと駆動制御の融合が、Teryx H2の「乗って楽しい」「どこでも行ける」という体験を実現しています。しかし、だからこそ気をつけたいのが、泥・水・小石・紫外線など過酷な自然環境によるボディへのダメージです。
特に電子制御ユニット(ECU)やサスペンションセンサー周辺は、雨天走行や洗車時に水が入り込むと故障リスクが高まるため、適切な防水・防汚対策が必要不可欠です。そこで、SOUPでは、こうした精密コンポーネントが多く搭載されたオフロードビークルに対し、セラミックコーティングとともにガスプライマーの施工をおすすめしております。
ガスプライマーによって下地密着性を高めたうえでセラミックコーティングを施工することで、Teryx H2のような複雑な樹脂形状や金属パネルに対しても均一な被膜形成が可能となり、水や泥の付着を大幅に低減。特にタイヤハウスやサスペンションアーム周辺は、跳ね石や粘土質の土が付着しやすいため、コーティングによって洗浄性が格段にアップします。
価格・装備・ライバル比較から見たTeryx H2の真価とは

Kawasaki Teryx H2の魅力は、スペックだけでは語り尽くせません。重要なのは「コストパフォーマンス」──つまり、どこまでの走破性と装備を、いかなる価格で実現しているかという点です。
まずTeryx H2の価格帯を見てみると、ベースグレードで37,199ドルから、4シーターのデラックスモデルが43,199ドル、さらに5人乗りの最上級グレードでも43,699ドルとなっており、Polaris RZR Pro R(4人乗り仕様)やCan-Am Maverick R(同様の装備条件)と比べておよそ10〜15%ほど安価な設定です。
価格だけを見れば「安いUTV」と誤解されるかもしれませんが、装備面を比較すると、むしろ先進性で上回っている部分も多く存在します。たとえば、10インチのGarmin製インフォテインメントディスプレイを搭載したのはDeluxeモデルのみではあるものの、そのUIは直感的で、オフロードのルートナビや車両情報、スマートフォン連携機能などが非常にスムーズ。スマホ世代のドライバーにも好まれる仕様と言えるでしょう。
全長159.4インチ、全幅74.0インチのボディサイズと126インチのホイールベースは、PolarisやCan-Amのフラッグシップモデルよりも若干コンパクトで、日本の山間部や林道のような狭いフィールドにおいては大きなアドバンテージです。加えて、Teryx H2の車重は2,373ポンド(約1,076kg)。これはPolaris RZR Pro R(2,480ポンド)やCan-Am Maverick R(2,640ポンド)と比べても軽量で、トレイラーでの牽引や整備性でも優れた点となります。

SOUPでは、こうした最新UTVへの対応として、ボディ全体へのセラミックコーティングに加え、ホイールコーティング、アンダーガード部の保護施工、ナビやスクリーン周りのコーティングまで、車両の仕様に応じた最適なメニューをご用意しております。
最後に、こうした特殊な車両のコーティングをご検討いただく際、SOUPでは無料の代車(最長2週間)をご用意しております。遠方からお越しのお客様や長期施工をご希望の方でも安心してお預けいただけます。
Kawasaki Teryx H2──それは単なるスペックの塊ではなく、まさに「走り」と「賢さ」を両立させた一台。そして、そんな一台にこそ、私たちSOUPのセラミックコーティングとガスプライマーによる保護技術が真価を発揮するのです。